はじめに
夏休みが終わり、また保育園・幼稚園での生活が始まると、子どもが急に「行きたくない」と言い出すことがあります。
長い休みの間に生活リズムが変わったり、家族と過ごす安心感に慣れたりしたことで、新学期の登園に不安を感じるのはごく自然なことです。
しかし、毎朝泣いてしまったり、着替えを嫌がったりすると、ママやパパも心配になってしまいますよね。
「うちの子だけ?」と焦る必要はありません。
多くの家庭で夏休み明けには同じような登園しぶりが見られます。
本記事では、保育園・幼稚園児が夏休み明けを安心して迎えられるように、家庭でできる工夫や親の心構え、そして先輩ママの実践アイデアをまとめました。
子どもと一緒に少しずつ気持ちを整えていけば、きっと笑顔で新学期の園生活をスタートできますよ。

なぜ夏休み明けは子どもが不安になるの?
夏休み明けに登園を嫌がるのは、決してめずらしいことではありません。
子どもにとっては長いお休みを終えて再び集団生活に戻るという、大きな環境の変化があるからです。
ここでは主な理由を整理してみましょう。
生活リズムの乱れ
夏休みはお出かけや実家への帰省などで、就寝・起床時間が遅くなりがちです。
夜更かしや昼寝の増加により、園生活のリズムに体がついていけず、朝の登園が一層つらく感じられることがあります。

家族と過ごす安心感からの切り替え
長期間、ママやパパと一緒に過ごすことで「家が一番安心できる場所」という気持ちが強くなります。
そのため、再び離れて過ごすことに不安や寂しさを感じやすくなるのです。
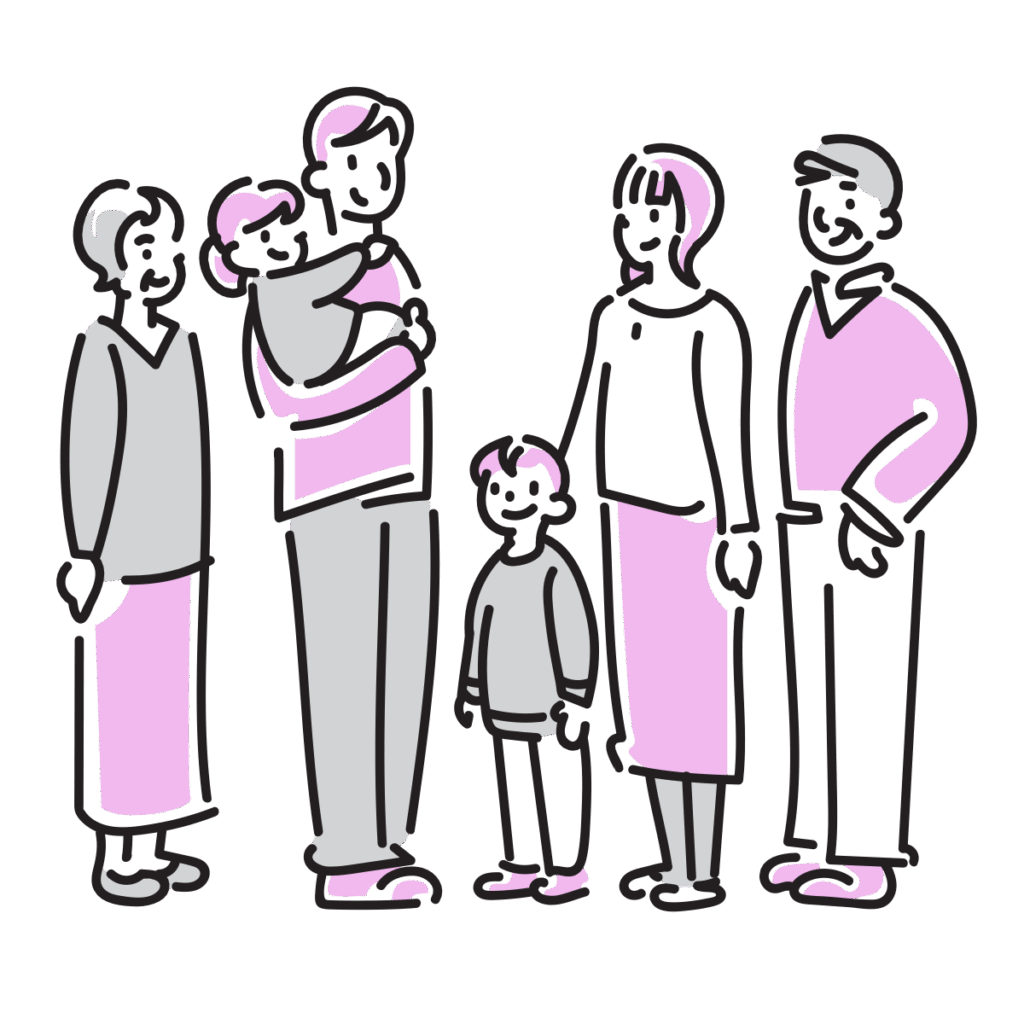
新しい環境への緊張
夏休み明けは、久しぶりに会う先生やお友達、行事の練習が始まるなどの環境が影響している場合もあります。
「久しぶりの園」=「少し不安な場所」と子どもが感じてしまうのはごく自然なことです。
心の成長の表れ
実は「登園しぶり」は、子どもの心が成長している証でもあります。
自分の気持ちを言葉や態度で表せるようになったからこそ「行きたくない」と伝えられるのです。
親としては困ってしまいますが、それは健やかな発達の一部と考えて良いでしょう。
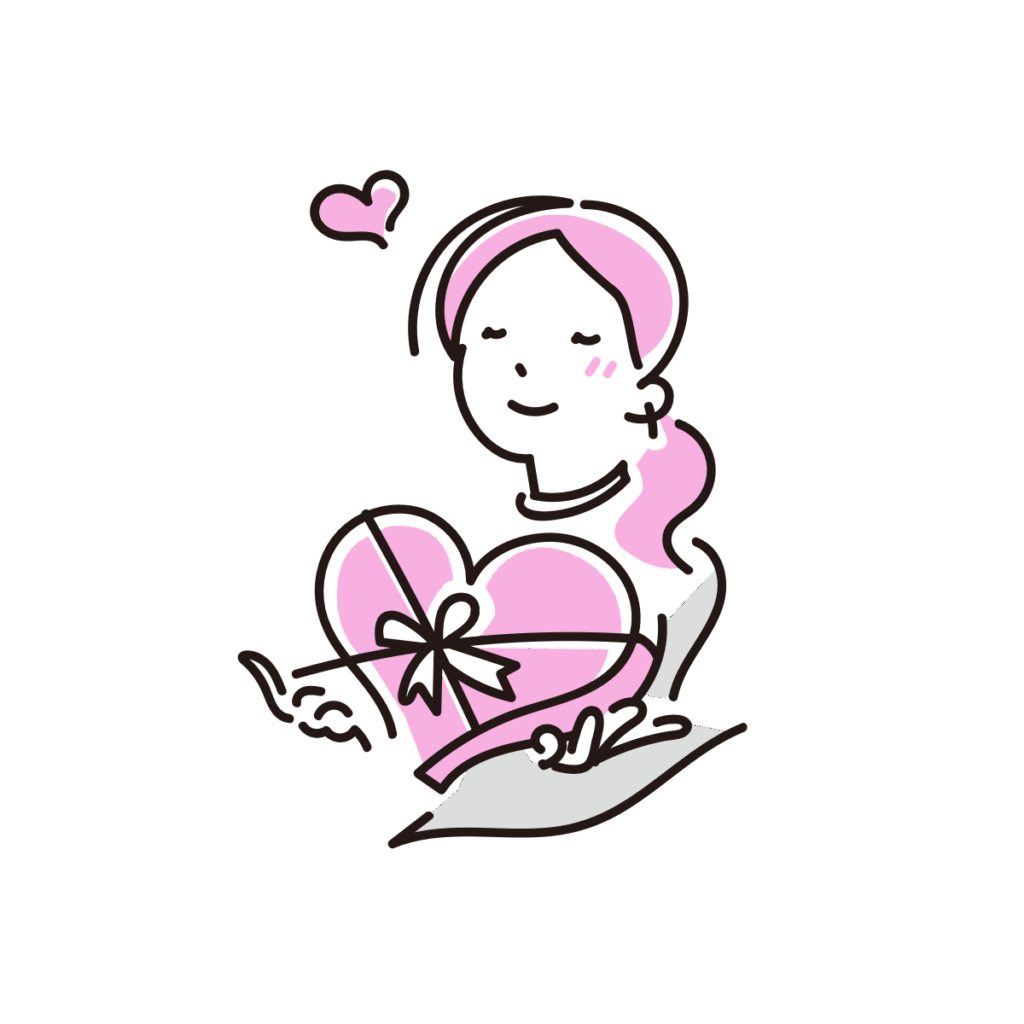
家庭でできる不安解消アイデア
生活リズムを少しずつ整える
夏休み中に崩れた生活リズムをそのままにしていると、朝起きるのがつらくなり、登園のハードルが高くなります。
新学期の1週間前くらいから、就寝・起床時間を園生活に合わせて戻していきましょう。
朝日を浴びる、朝食をしっかり食べるといった習慣も、子どもの体内リズムを整えるのに役立ちます。
園生活をイメージさせる会話をする
「先生に会えるの楽しみだね」「〇〇ちゃんと一緒に遊べるよ」と、園でのポジティブな場面を具体的にイメージできるような会話を心がけましょう。
過去に楽しかった出来事を思い出すのも効果的です。
親の言葉かけひとつで、子どもの気持ちはぐっと安心に傾きます。
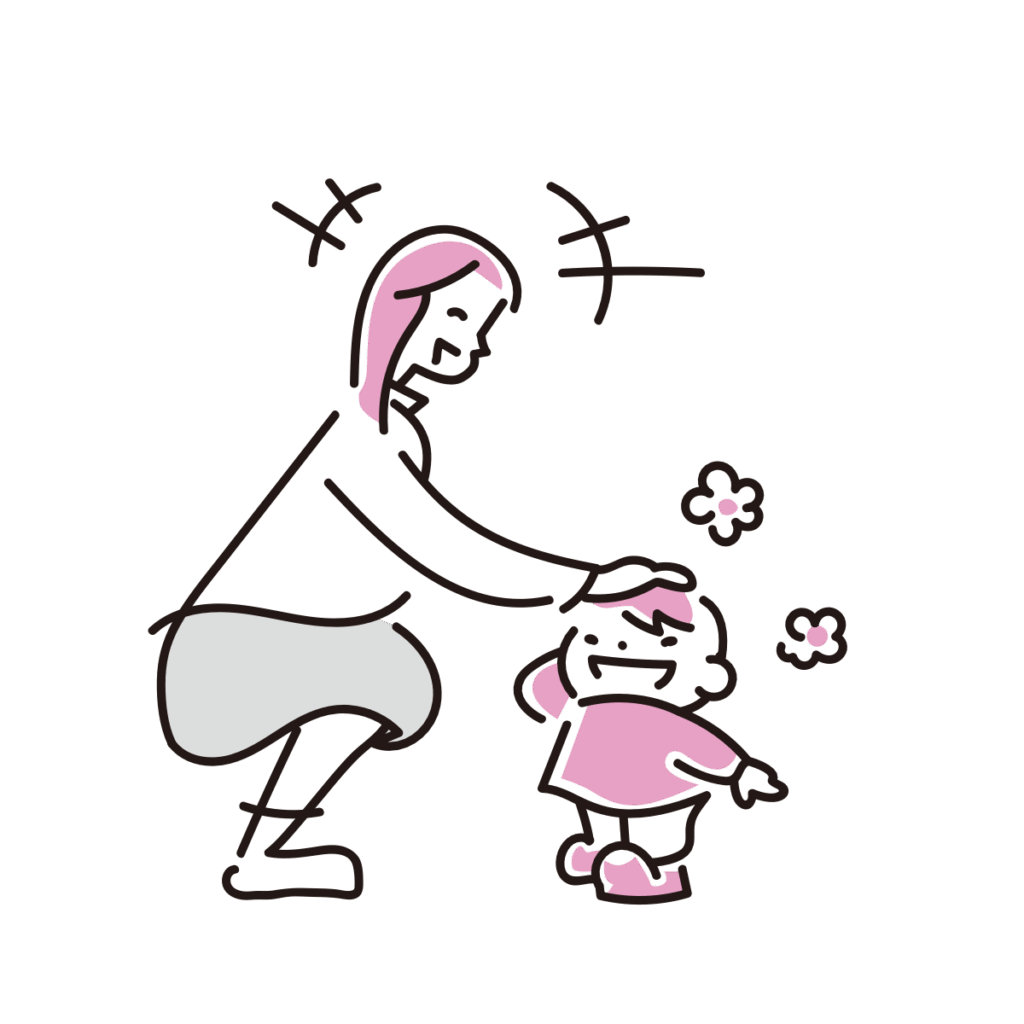
安心グッズを持たせる
お気に入りのハンカチや小さなマスコット、ママからの小さなお手紙など、子どもの心を支える“お守り”になるものを持たせるのもおすすめです。
園では持ち込みルールがありますが、許される範囲で子どもの安心材料になるものを準備してあげると、気持ちが落ち着きやすくなります。
次女の通っている保育園では、リュックやカバンにキーホルダーを付けるのはOKなので、その時に1番お気に入りのものを付けて行っています。
短時間から慣らす工夫をする
もし可能であれば、夏休み明けの数日間は早めのお迎えをして、園生活に少しずつ慣れていけるようにしましょう。
「今日は早く迎えに来てくれた」という経験は、子どもに安心感を与え、次の日の登園もしやすくなります。
無理に一気に通常モードに戻さず、スモールステップで進めることが大切です。
我が家では、早めにお迎えに行ったら行ったで「もっと遊びたかったのに〜」と言われて拍子抜けするなんてこともしばしば(笑)
行ってしまえば上手に切り替えができて、園生活を楽しめる子も多いですよ。

ママ・パパ自身の心構え
不安は一時的なものと知る
夏休み明けの登園しぶりは、多くの子どもに見られる一時的な反応です。
新しい環境に慣れるまでの「心の調整期間」と考えてみましょう。
早ければ数日、長くても1〜2週間ほどで落ち着くことが多いので、「今だけのこと」と捉えると気持ちが少し軽くなります。
園と連携して安心感を持つ
子どもが登園時に泣いていても、実際には園に入ってしまえばすぐに笑顔で遊んでいることもよくあります。
担任の先生と日々の様子を共有しておくと、親も安心できます。
「うちの子、園ではどうですか?」と一言聞くだけでも不安が和らぎますよ。
親の焦りを子どもに伝えない
子どもはママやパパの気持ちを敏感に感じ取ります。
親が「早く行ってほしい」「泣かないで」と焦ってしまうと、その緊張感が子どもに伝わり、不安が強まることも。
泣いていても「大丈夫、いってらっしゃい」「迎えに来るからね」と落ち着いて送り出すことが、子どもに安心感を与えます。
自分を責めない
「なんでうちの子は…」「私の接し方が悪いのかな」と自分を責める必要はありません。
子どもにとって登園しぶりは自然な成長の一部であり、親のせいではないのです。
ママ・パパ自身も無理をせず、時には息抜きをしながら子どもと向き合いましょう。

実際に効果があった先輩ママの工夫例
夏休み明けの登園しぶりは、多くの家庭で経験しています。
ここでは、実際に試してみて「効果があった!」という先輩ママの工夫をご紹介します。
朝のお支度を歌にして楽しく
「なかなか着替えてくれなかったので、『お着替えの歌』を即興でつくりました。
歌いながら一緒にやると笑顔が出て、気づいたら準備完了。
朝のバタバタがぐっとラクになりました」
意外に子供の方が即興ソングが得意だったなんてことも!
新しいアイテムで気分をリフレッシュ
「キャラクターのお弁当袋やハンカチを新調したら、子どもが『早く使いたい!』と楽しみに登園するようになりました。小さな変化でもモチベーションアップにつながります」
数千円で子供が楽しく登園できたら、こんなに安いものはないですよね♪
特別なお楽しみを用意する
「夏休み明けの1週間だけ、帰宅後に“特別おやつタイム”を設けました。
『今日は何かな?』と楽しみにしてくれて、朝も前よりスムーズに登園できました」
スモールステップで安心感を育てる
「最初の数日は早めに迎えに行き、『今日は短い時間で頑張れたね』とたくさん褒めました。少しずつ通常の時間に戻したら、子どもも無理なく園生活に慣れていきました」
どの工夫も特別な準備は必要なく、すぐに取り入れられるものばかり。
小さな工夫が、子どもにとって大きな安心や楽しみに変わります。
まとめ|子どもの不安は親子で一緒に乗り越えられる
夏休み明けに保育園や幼稚園へ行きたがらないのは、多くの子どもに見られる自然な反応です。
生活リズムの変化や、家族との安心感から離れる不安、新しい環境への緊張などが重なって、登園しぶりとなって表れるのです。
けれども、これは一時的なもの。
親ができるのは
「生活リズムを整える」
「安心グッズを持たせる」
「園での楽しいことを思い出させる」
といった小さな工夫と、子どもの気持ちを受け止めてあげることです。
また、ママやパパ自身が「不安は今だけ」「無理に泣き止ませなくてもいい」と心に余裕を持つことも大切です。
先生との連携や、先輩ママたちのアイデアを参考にすれば、少しずつ笑顔で登園できるようになります。
夏休み明けは親子にとってちょっとした試練のように感じるかもしれませんが、乗り越えた経験は子どもの自信にもつながります。
焦らず寄り添いながら、また楽しい園生活をスタートさせていきましょう。
こちらの記事もおすすめ!
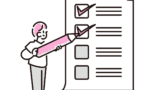
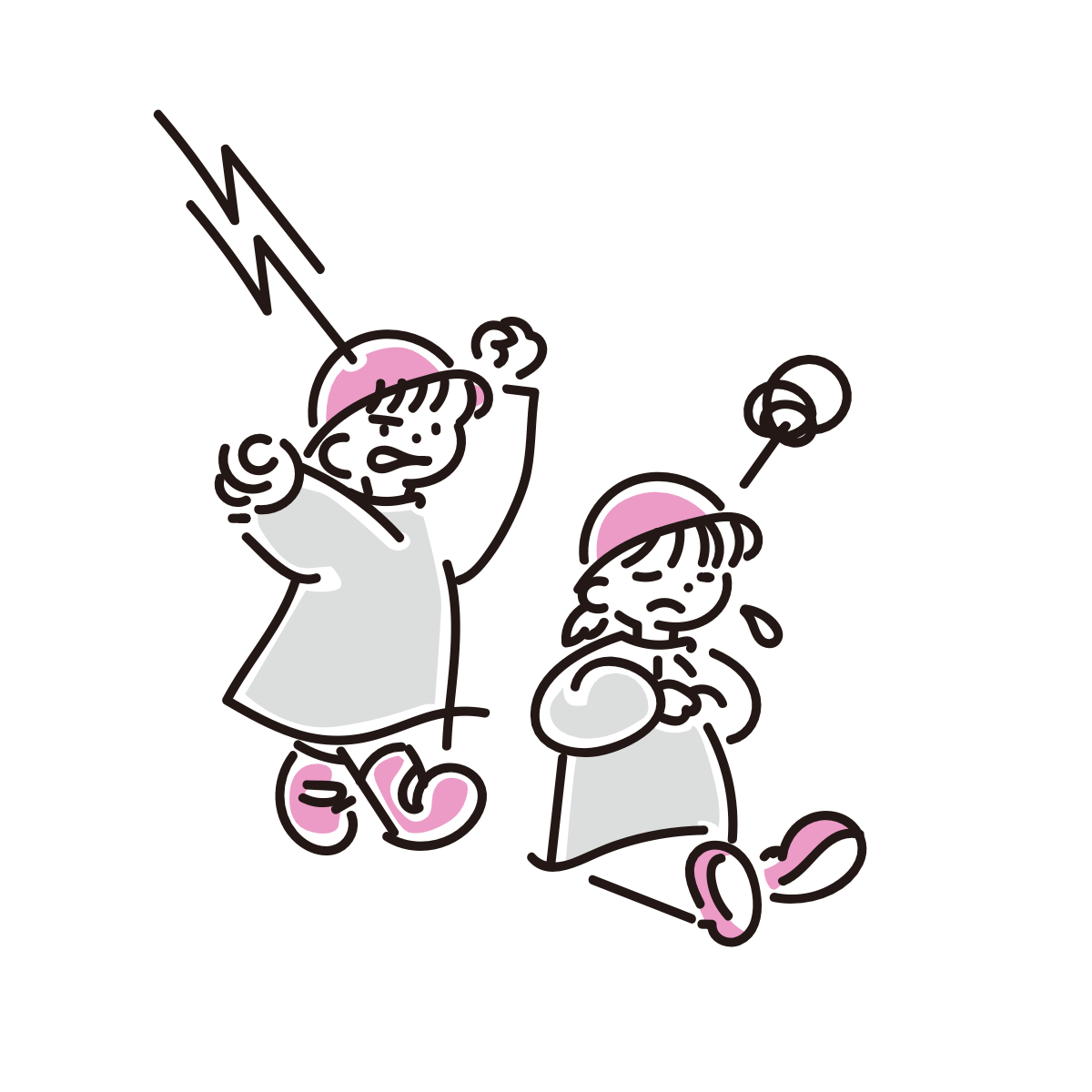
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bb99e2d.50c36196.4bb99e2e.054554e7/?me_id=1284609&item_id=10000477&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fwaabbit%2Fcabinet%2Fg%2Fkeyname_miffy%2Fthumbnail-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bb9a114.dbd484d6.4bb9a115.f7b94766/?me_id=1403490&item_id=10003466&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frbranshes%2Fcabinet%2F25%2Fr-16-5686-501-32_02.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bb99982.559d4347.4bb99983.61893e08/?me_id=1300911&item_id=10004229&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsime-fabric%2Fcabinet%2Fpic43%2Fskdc4-sime-omk.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bb9a1fb.0c28f0b9.4bb9a1fc.379410b3/?me_id=1370173&item_id=10001378&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fniziiro-store%2Fcabinet%2F06791140%2F06905170%2F09620166%2Fmt-b0c77wy6qn_nm25a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

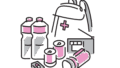
コメント