はじめに
子育てと仕事に追われる毎日。
「もし災害が起きたら、子供をちゃんと守れるかな…」と、ふと不安になることはありませんか?
特にワーママは、仕事で家を空ける時間も多く、子供だけで過ごす場面や、家族がそろわない時間帯に災害が起きる可能性もあります。
だからこそ、普段の暮らしの中に「防災の準備」を少しずつ取り入れておくことが大切です。
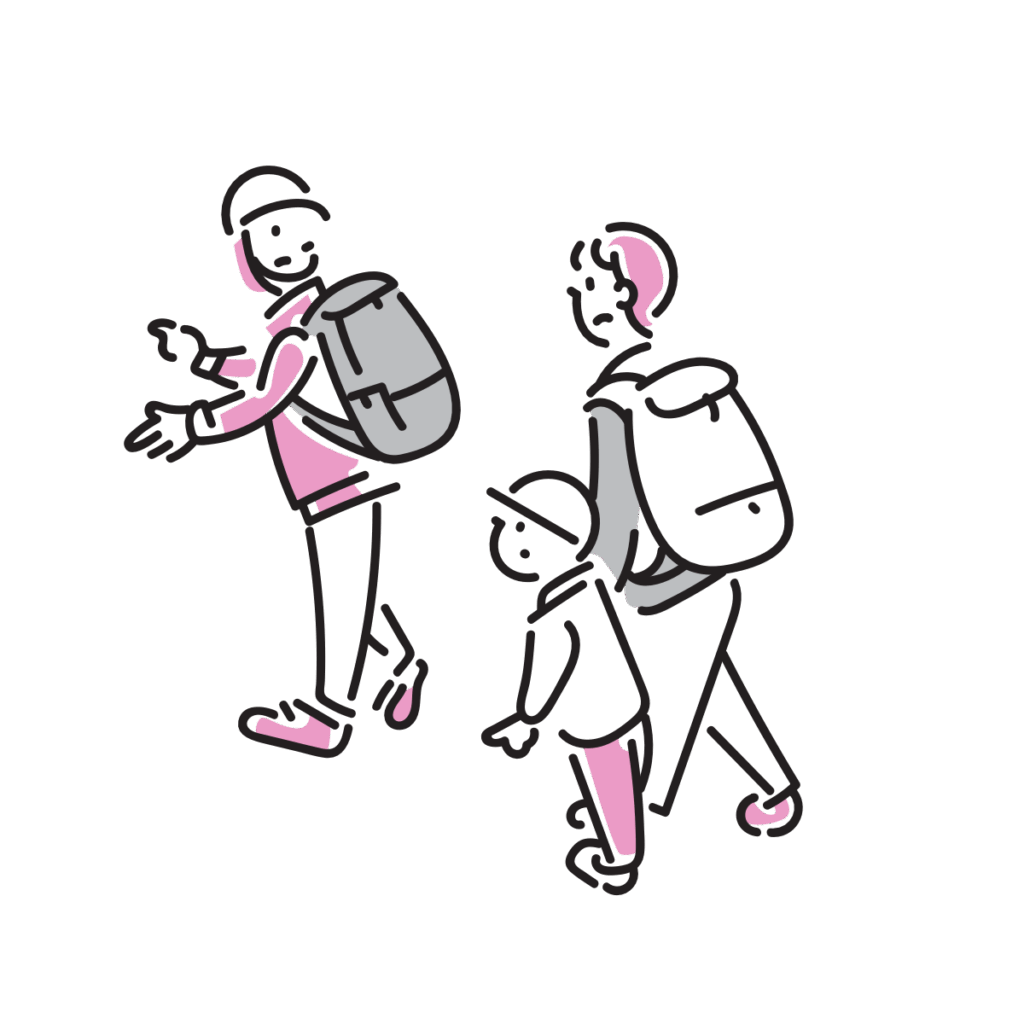
防災と聞くと「特別な準備」「大がかりなこと」と構えてしまいがちですが、実は子供と一緒に楽しみながらできる工夫もたくさんあります。
避難ルートを散歩がてら歩いてみたり、非常食を「おやつタイム」として食べてみたり…。小さな積み重ねが、いざという時に大きな安心につながります。
この記事では、子供と一緒に楽しみながらできる防災練習のアイデアや、ワーママでも無理なく続けられる日常の備え方をご紹介します。子供にとっても自然に身につく習慣となり、家族みんなの安心を育むきっかけになれば嬉しいです。
子供と一緒に始める「日常の防災準備」
防災対策は「特別なこと」として意識すると長続きしません。
ワーママにとっては、忙しい日常の中で少しずつ取り入れる工夫が大切です。子供と一緒に楽しみながら実践することで、自然と習慣になり、いざという時にも慌てず行動できるようになります。
防災を特別なことにしない「普段使い」の意識
防災グッズを棚にしまい込むのではなく、普段から少しずつ使う「ローリングストック」を意識すると、子供も親しみやすくなります。
例えば、おやつ代わりに非常食を食べてみたり、懐中電灯を「探検ごっこ」で使ったりするのもおすすめです。「防災=難しいこと」ではなく、子供にとって身近な体験として落とし込むと続けやすくなります。

子供にあった備えを考える(年齢別の工夫)
子供の年齢によって必要な備えや練習の仕方は変わります。
• 未就学児:避難のときに手をつなぐ練習や、「お名前・住所を言える」ことを意識。
• 小学校低学年:非常用リュックを一緒に準備して、自分で持てる範囲の荷物を持たせる。
• 小学校高学年:避難経路の確認や、家族が離れてしまったときの集合場所を一緒に決める。
成長に合わせて段階的に備えることで、子供自身も「自分でできることがある」と実感でき、防災意識を持つきっかけになります。
親子でできる防災練習アイデア
防災の知識は「聞いただけ」ではなかなか身につきません。
実際に体験しながら学ぶことで、子供も自然に覚えていきます。特に小さな子供にとっては、遊びの延長で取り組める練習が効果的です。
親子で楽しく取り組める防災練習のアイデアをご紹介します。
避難経路を一緒に歩いて確認する
災害が起きたときにすぐ行動できるように、日常の散歩や買い物のついでに「避難所まで歩いてみる」のがおすすめです。実際に歩いてみると「ここは暗いと怖い」「ここは狭くてベビーカーだと通りにくい」など気づきが出てきます。
子供と一緒に「安全な道」を確認しておくと安心です。

家の中でできる防災ごっこ(暗闇体験・非常食体験など)
停電を想定して、夜に電気を消して懐中電灯やランタンだけで過ごす「暗闇体験」や、非常食を実際に食べてみる「試食会」も防災練習のひとつ。
遊びのように取り入れることで、子供にとっても印象に残りやすく、いざという時に役立ちます。
公園やお出かけ先でも避難場所を探す習慣づけ
普段よく行く公園やショッピングモールなどでも「もしここで地震があったらどこに避難する?」と声をかけてみましょう。お出かけ先でも意識することで、子供自身が「避難場所を探す力」を身につけていきます。家族が一緒にいないときの行動を考える練習にもなります。
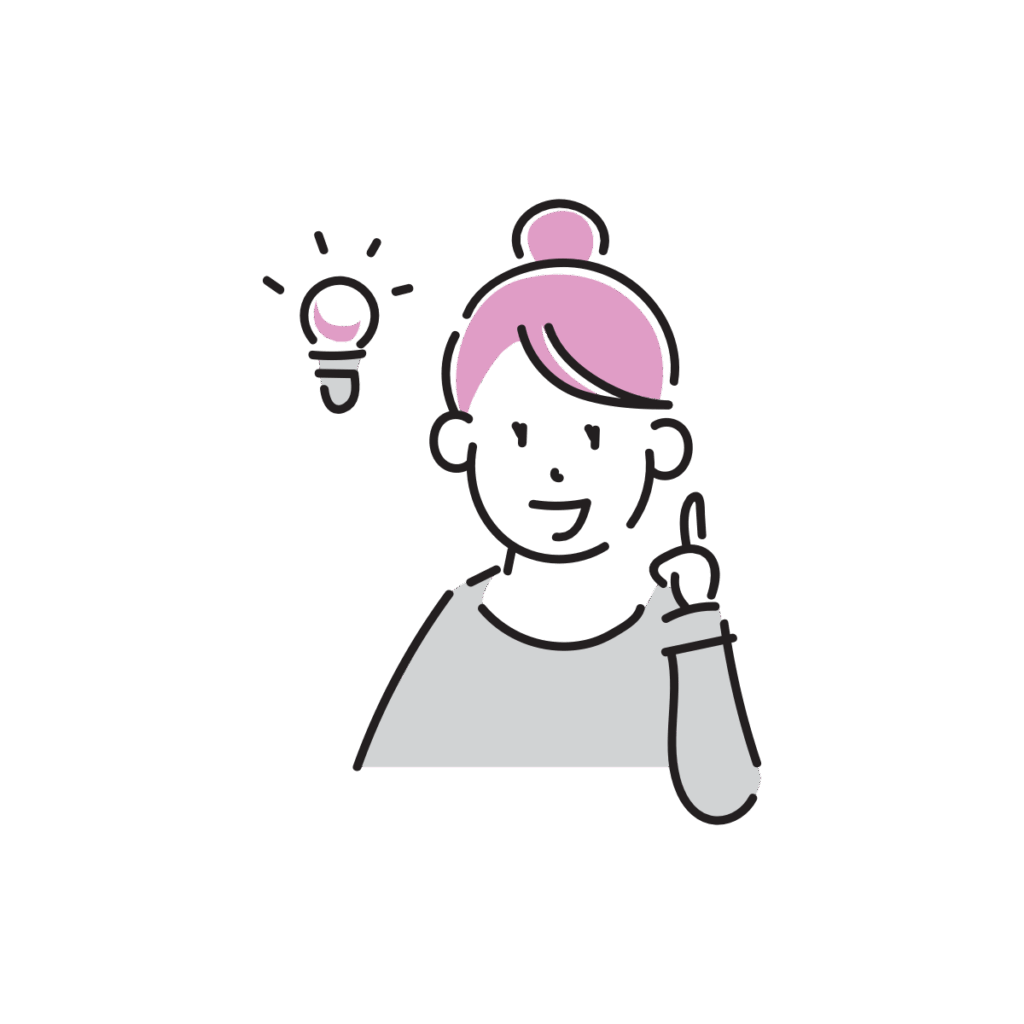
子供と一緒に用意する防災グッズ
防災グッズは「親が用意しておくもの」と思われがちですが、子供自身が準備に関わることで、いざという時の安心感が大きく変わります。「自分のための持ち物」があるだけで、心細さを和らげる効果もあります。
子供が持てる「マイ防災リュック」を作ろう
子供用には、大人と同じものを詰め込む必要はありません。
お気に入りのリュックに「水筒・おやつ・ハンカチ・タオル・小さなおもちゃ」など、子供でも持ち歩ける重さで準備しましょう。自分のリュックを持つことで「避難のときに持ち出す大切なもの」という意識が芽生えます。

ワーママ目線でそろえたい時短&安心アイテム
忙しいワーママにとって、防災グッズは「使いやすさ」が大事です。
例えば:
• 開けやすいパッケージの非常食
• 電池不要で手回しできるライトやラジオ
• 個包装のウェットティッシュやおしりふき
これらは子供のケアに役立つだけでなく、日常生活でも使えるので「備えながら使う」ローリングストックに適しています。
定期点検を親子で一緒に楽しむ工夫
防災グッズは用意して終わりではなく、定期的に中身を見直すことが大切です。
例えば「季節の変わり目にチェックする」「誕生日や記念日に点検する」など、親子でイベント感覚にすると続けやすくなります。
子供が「もう小さなおもちゃはいらないな」と感じたら、中身を一緒に更新するのも良いきっかけになります。
ワーママでも続けやすい「習慣化のコツ」
防災は「一度準備して終わり」ではなく、生活の中に少しずつ取り入れて習慣にすることが大切です。
ただ、仕事や家事、子育てで忙しいワーママにとっては「特別な時間をつくる」のは難しいもの。そこで、毎日の暮らしに無理なく組み込めるコツをご紹介します。
月に1回、子供と一緒にチェックする仕組みづくり
例えば「月初めの日曜日は防災の日」と決めて、非常食の賞味期限や懐中電灯の電池を子供と一緒に確認するのがおすすめです。ゲーム感覚で「賞味期限探し」をすると、子供も楽しみながら参加できます。
うちでは賞味期限が近いものがたくさん見つかったら、その日はパーティと称して様々なメニューを並べて楽しんでいます♪
遊び感覚で続けられる防災アクティビティ
避難の合図を決めて「合図が鳴ったら安全な場所に集まる」という遊びを取り入れると、自然と行動が身につきます。普段から防災をゲームやごっことして取り入れることで、無理なく続けられます。
うちの子が通っている保育園では低年齢から「ダンゴムシのポーズ」を教えてくれます。音が鳴ったら誰が1番初めにダンゴムシになれるか競争するのも楽しいです。
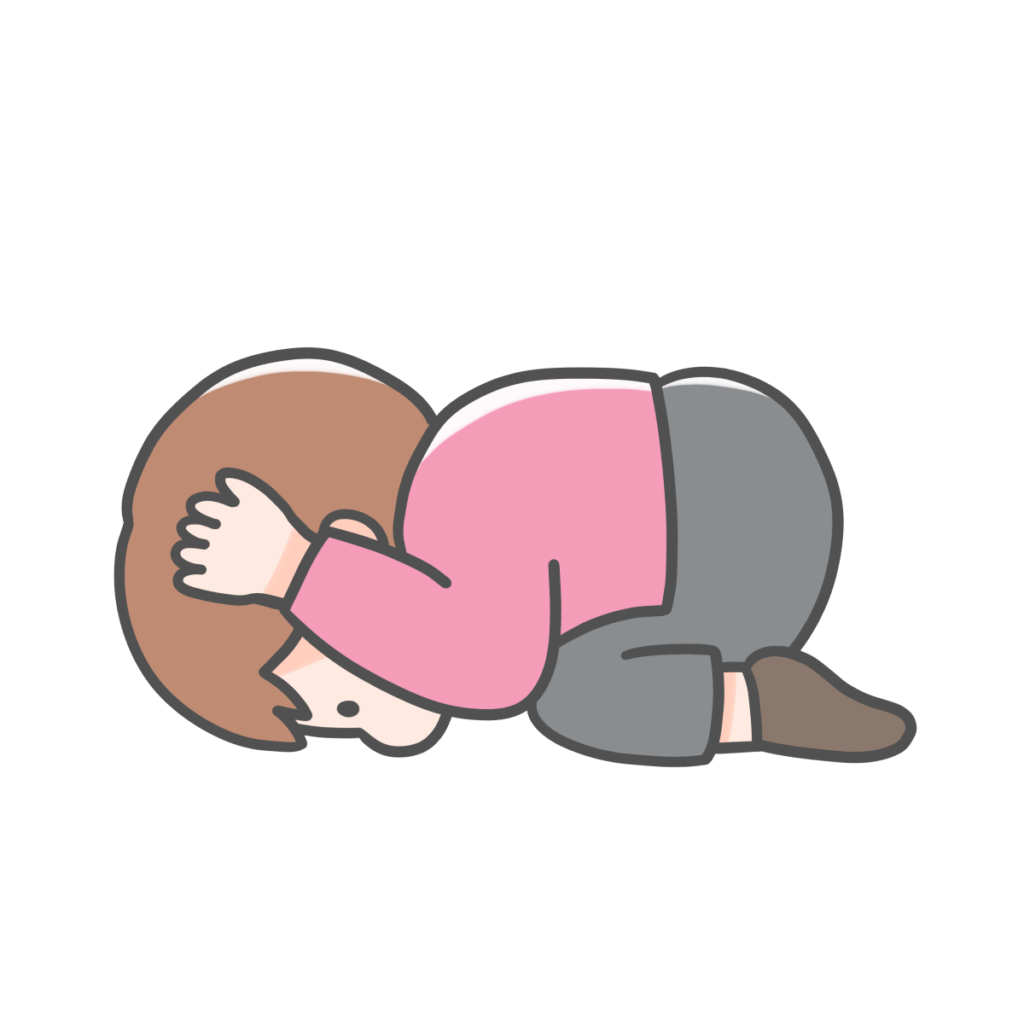
家族みんなで共有する「防災ルール」
「災害が起きたら〇〇公園に集合」「学校から帰れないときは〇〇に避難」など、シンプルなルールを決めて家族で共有しましょう。冷蔵庫やリビングの壁に貼っておくと、子供も自然と覚えてくれます。
家族全員が同じルールを知っていることは、ワーママの安心にもつながります。
まとめ|子供と一緒だからこそできる日常の防災
防災は「完璧な備えを一度で整えること」ではなく、日常の中で少しずつ積み重ねていくことが大切です。子供と一緒に練習や準備をすることで、防災が特別なものではなく「暮らしの一部」になっていきます。
避難経路を歩いて確認する、非常食を一緒に試してみる、マイ防災リュックを作る…。どれも大がかりなことではなく、日常に自然と取り入れられるものばかりです。
こうした小さな体験は、いざという時に子供を守る力につながり、ワーママ自身の安心にもなります。
忙しい日々の中で「今日はこれをやってみよう」と無理のないペースで取り入れていけば十分です。子供と一緒だからこそ、遊び感覚で学べることも多くあります。
家族の防災力を高める第一歩を、ぜひ今日から始めてみませんか。
こちらの記事もおすすめ!
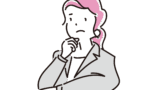
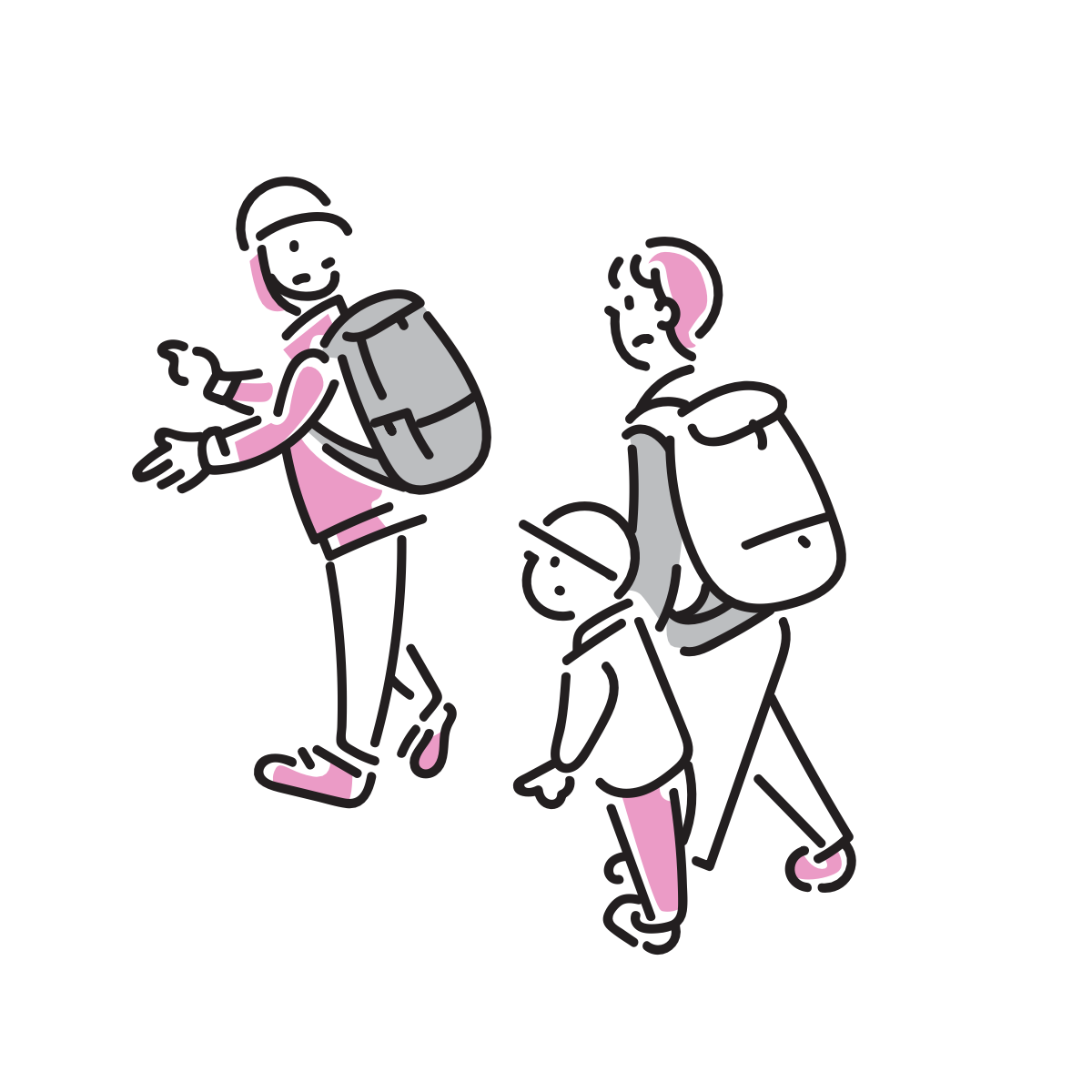
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c265239.888d2489.4c26523b.25f37ce8/?me_id=1293781&item_id=10000016&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpro-bousai%2Fcabinet%2F09585814%2Fthumbs%2Famazon2021kids.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c265082.2eb7b505.4c265083.20086465/?me_id=1370332&item_id=10000792&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fshopdirectishii%2Fcabinet%2F08183873%2F10435766%2Fimgrc0175491885.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c264301.ae933952.4c264302.19c91cd3/?me_id=1205937&item_id=10027048&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-kurashi%2Fcabinet%2Fmain-img%2F020%2Fmain-34530_t.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c264451.72c74611.4c264452.d942cc19/?me_id=1202803&item_id=10001724&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsaibou%2Fcabinet%2Fhijoshoku%2Fset%2F7kihon-top7.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c26458f.bd0cad53.4c264590.510e5672/?me_id=1297605&item_id=10002599&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fymx-shop%2Fcabinet%2F04764783%2F04766589%2Fymx1-058_tmb-5_s.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4c2649fa.e9e1691d.4c2649fb.b03138d2/?me_id=1251161&item_id=10022769&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fhellobungu%2Fcabinet%2F09775169%2F09782692%2F11000392%2F2951_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
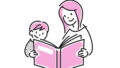
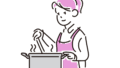
コメント