はじめに
4歳は、ことばの世界がぐんと広がり、想像の翼をのびのびと広げられる大切な時期です。
自分の気持ちを少しずつ言葉で表現できるようになり、物語を聞いて「どうして?」「こうだったらいいのに」と考える力も育ってきます。
そんな成長の真っ只中にある4歳の子どもたちに、季節を感じられる絵本はぴったり。
特に秋は、落ち葉やどんぐり、食べもの、行事など、日常の中に発見やワクワクがたくさん隠れています。絵本を通して「今」の体験と結びつけることで、心に残る読書体験へとつながります。
この記事では、長年図書館で子どもたちに絵本を届けてきた司書の視点から、4歳の今だからこそ読んでほしい「秋の絵本」をご紹介します。
親子で過ごすひとときが、秋の深まりとともにもっと特別な時間になりますように。
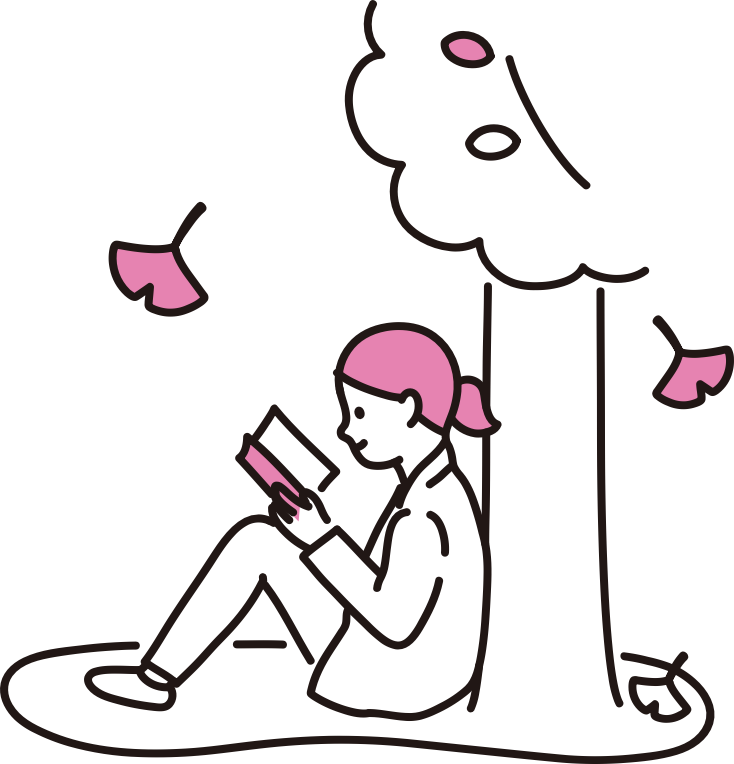
4歳にぴったり!司書おすすめ秋の絵本
秋の自然を感じられる絵本
• 『どんぐり どんぐり』(降矢なな/作 福音館書店)
森の中、かあさんりすがどんぐり拾いに出かけます。落ち葉のなかから「みーつけたひとーつ」親子で声を出して一緒に数えてみると盛り上がります。森の風景が美しい絵本です。
• 『やきいもするぞ』(おくはらゆめ/作・絵 ゴブリン書房)
落ち葉集めからやきいもづくりまでのワクワクを描いた一冊。秋の生活体験と絵本をつなげるのにぴったりです。ちょっとおマヌケな大会を繰り広げる動物たちと一緒に参加してみて下さい。
食欲の秋を楽しむ絵本
• 『さつまのおいも』(中川ひろたか/作 村上康成/絵 童心社)
おいもたちの力強くユーモラスな姿が大人気。読むと子どもも思わず笑顔になり、秋の味覚を楽しく感じられます。一生懸命頑張るイモたちの姿が健気でかわいらしいです。読んだら焼き芋が食べたくなること間違いなし!?
• 『くだもの』(平山和子/作 福音館書店)
秋の果物がリアルに描かれた絵本。あまりにみずみずしく美味しそうな果物の絵を見ながら「食べたい!」と声に出す4歳の姿が想像できる1冊です。
行事や文化に触れられる絵本
• 『いもいもほりほり』(西村敏雄/作 講談社)
3匹のこぶたが芋ほりに出かけます。「いもいも ほりほり いもほりほり」リズミカルなセリフについつい口ずさんでしまいます。こぶたたちは無事に焼き芋が食べられるのでしょうか!?
• 『おつきみうさぎ』(中川ひろたか/作 村上康成/絵 童心社)
今日はお月見。すすきを取って、お団子を作って・・・。
お月見の行事をうさぎと一緒に体験できる絵本。日本の風習を自然に知るきっかけになる一冊です。
もっと読みたい人へ
• 『どんぐりと山猫』(宮沢賢治/作 高野玲子/絵 偕成社)
宮沢賢治の不思議なお話を、やわらかな絵で表現。4歳の「なぜ?どうして?」に寄り添いながら、秋の森の空気を感じられます。「わーわー」喧嘩するどんぐりにくすっと笑ってしまいます。
• 『ハロウィーンってなぁに?』(クリステル・デモワノー/作 主婦の友社)
ちびっこ魔女のビビと一緒にハロウィーンを楽しみましょう。ハロウィーンの由来やかぼちゃのランタンの作り方、文化の学びの一歩としてもおすすめです。
• 『いもほりコロッケ』(おだしんいちろう/文 こばようこ/絵 講談社)
ぼうしをかぶって、軍手をはめて、水筒かけて、スコップ持って、いざじゃがいも掘りへ!!たくさん掘ったじゃがいもでお母さんといっしょにコロッケを作ります。そのコロッケの美味しそうなことといったら!食育にもおすすめの1冊です。
• 『たぬきのおつきみ』(内田麟太郎/作 山本孝/絵 岩崎書店)
秋になって稲穂が実り、野菜もがくさん取れました。豊作に村人たちもたぬきも大喜びです。今夜はお月見。お月様はよろこんでくれるかな・・・?
読み聞かせをもっと楽しむコツ
4歳の集中力に合わせた読み方の工夫
4歳になると、ストーリーを理解する力が育ち、長めのお話にも少しずつついてこられるようになります。
ただし集中できる時間はまだ限られており、およそ10分前後が目安です。
そのため、一度に長い物語を最後まで読もうとするよりも、章立てや展開の切れ目で区切りをつけて「続きはまた明日ね」と楽しみを残してあげるのがおすすめです。そうすると「早く続きが聞きたい!」と翌日の楽しみにもなり、親子の習慣づくりにもつながります。
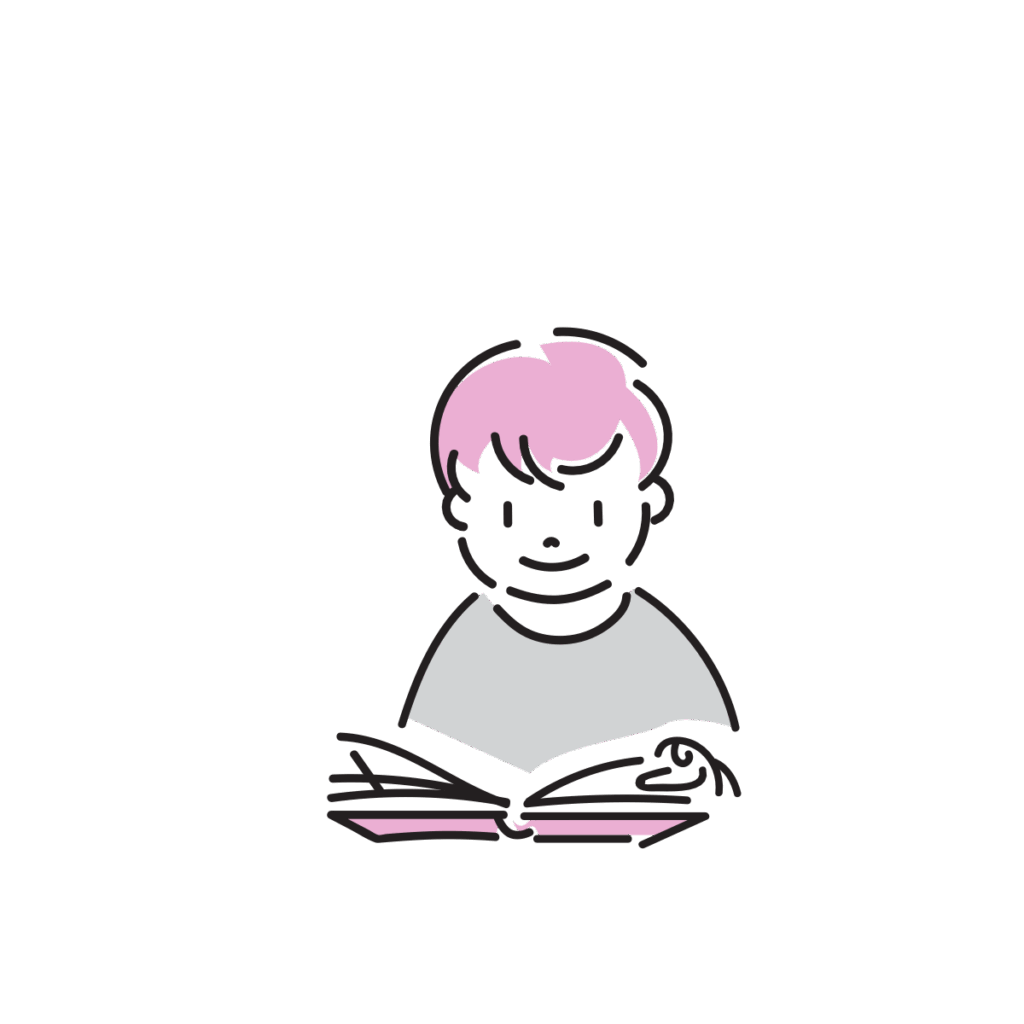
親子の会話を広げる質問や声かけ
読み聞かせは「読むだけ」で終わらせず、親子の会話に広げることで楽しさが倍増します。
たとえば『どんぐり どんぐり』を読んだあとに「明日は公園でどんぐりを探してみようか」と誘ったり、『おつきさまこんばんは』の後に「お月さまってどんな顔に見えた?」と尋ねたりすると、子どもの想像力がぐんとふくらみます。
質問は正解を求めるものではなく、「どう思った?」「どんなふうに見えた?」という気持ちを引き出すことが大切です。親に受け止めてもらえる安心感が、子どもの言葉を育てていきます。
夜の読み聞かせに取り入れたい演出
秋の夜長は、読み聞かせにぴったりの季節。寝る前に少し照明を落として、静かな声で読んであげると、安心して眠りに入る準備ができます。
さらに、声のトーンや速さを変えるだけでも雰囲気は大きく変わります。例えば、わくわくする場面は少し早口で、静かなシーンはゆっくりと。子どもは物語だけでなく、親の声の響きそのものを楽しんでいます。
読み聞かせを親自身のリフレッシュに
忙しい日々の中で「読まなきゃ」と義務に感じてしまうこともあるかもしれません。
でも、絵本を読む時間は親にとっても立ち止まれる貴重なひとときです。子どもが笑ったり驚いたりする表情を見ているだけで、疲れがふっと軽くなることもあります。
「今日は2冊読めたらいい」「寝る前にお気に入りの1冊だけ」など、無理のない範囲で取り入れることで、親子にとって心地よい絵本時間になります。
子どもはママのことが大好きで、ママの好きなものを知りたがります。「ママこの絵本が気になったんだけど、一緒に読んでみない?」と声をかけるのもおすすめです。
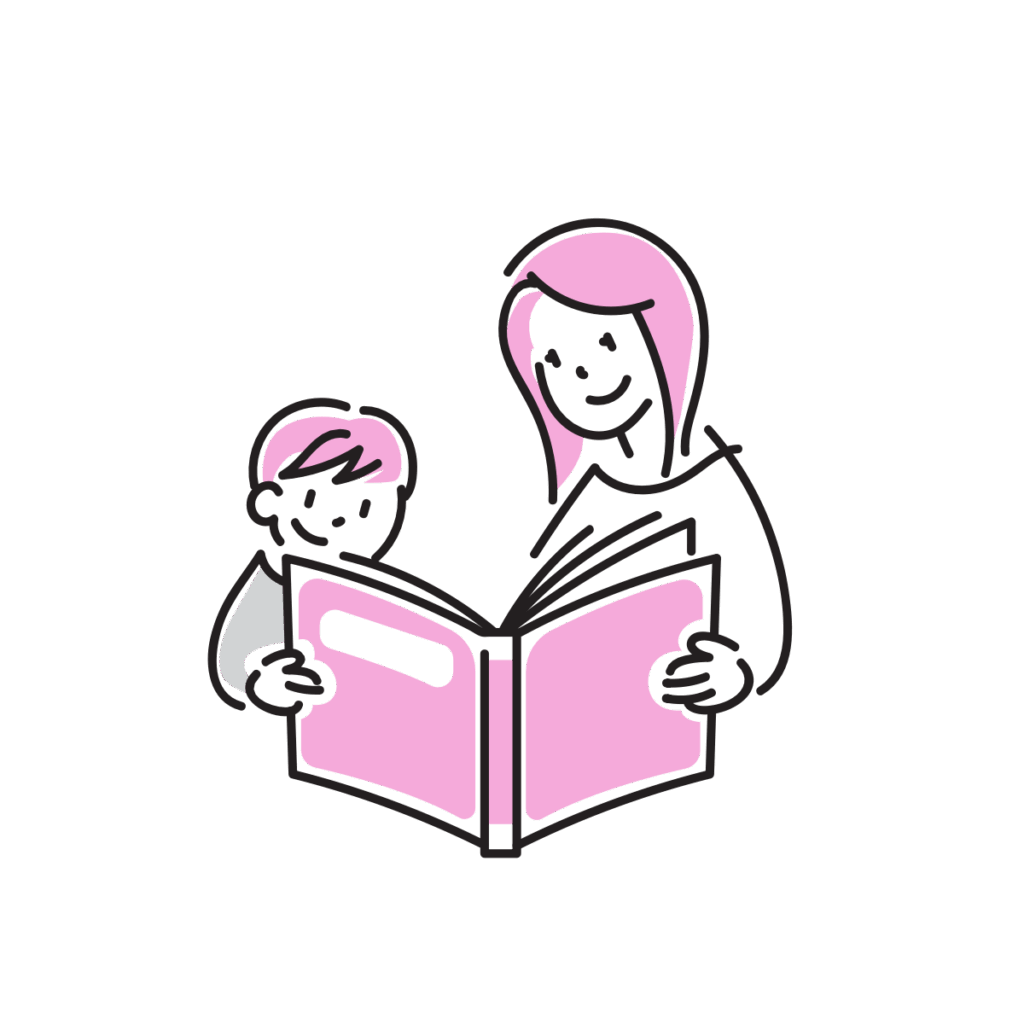
図書館司書が伝えたい絵本の魅力
同じ本を繰り返し読む大切さ
4歳頃は、お気に入りの絵本を何度も「読んで!」とせがむ時期です。同じ物語を繰り返すことで、ことばのリズムや展開を覚え、自分の言葉として表現できるようになります。司書としても、この「繰り返し体験」をとても大切にしています。
親子で季節の絵本を楽しむメリット
秋の絵本は、自然や食べもの、文化などを身近に感じさせてくれる宝物。親子で一緒に読むことで、「季節を楽しむ心」が子どもの中に育まれます。後々の読書習慣の基盤にもつながります。
まとめ
4歳は、ことばや感性がぐんと育つ大切な時期です。
秋という季節には、どんぐりや落ち葉、さつまいもやお月見など、子どもの五感を刺激するテーマがたくさんあります。絵本を通してそれらを体験することで、日常の発見や「もっと知りたい!」という気持ちにつながります。
今回ご紹介した絵本は、どれも司書としておすすめしたい作品ばかり。どの本も、4歳の「今」を大切にしながら、親子で一緒に楽しめる秋の魅力を届けてくれます。
ぜひこの秋は、絵本の世界を通して子どもと一緒に季節を感じ、親子の時間をより豊かにしてみてください。
読んだ絵本が、秋の思い出の1ページとして心に残りますように。
こちらの記事もおすすめ!


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/342c9ea6.c6ef30cf.342c9ea7.1a55ae9b/?me_id=1213310&item_id=19193150&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3768%2F9784065123768.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/342c9ea6.c6ef30cf.342c9ea7.1a55ae9b/?me_id=1213310&item_id=21034498&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7352%2F9784834087352_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47a05791.47c0bb96.47a05792.84b88d28/?me_id=1285657&item_id=12359568&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F00356%2Fbk4902257246.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/342c9ea6.c6ef30cf.342c9ea7.1a55ae9b/?me_id=1213310&item_id=11344063&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4940%2F49400563.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/342c9ea6.c6ef30cf.342c9ea7.1a55ae9b/?me_id=1213310&item_id=10103239&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8531%2F9784834008531.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47a05791.47c0bb96.47a05792.84b88d28/?me_id=1285657&item_id=12006078&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F00295%2Fbk4061324799.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/342c9ea6.c6ef30cf.342c9ea7.1a55ae9b/?me_id=1213310&item_id=10981247&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4940%2F49400596.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/342c9ea6.c6ef30cf.342c9ea7.1a55ae9b/?me_id=1213310&item_id=10235250&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4108%2F9784039634108.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/342c9ea6.c6ef30cf.342c9ea7.1a55ae9b/?me_id=1213310&item_id=11905306&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5005%2F9784072525005.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/342c9ea6.c6ef30cf.342c9ea7.1a55ae9b/?me_id=1213310&item_id=16379843&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F5371%2F9784061325371.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/342c9ea6.c6ef30cf.342c9ea7.1a55ae9b/?me_id=1213310&item_id=11187117&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F4871%2F9784265034871.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/479f822b.d97a7202.479f822c.973f5bda/?me_id=1337032&item_id=10000208&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fe-tech-rshop%2Fcabinet%2Fpicturebook%2F9784494042807%2Fwrapping009.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
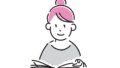

コメント