冬休みになると、いつもより時間に余裕があるはずなのに、なぜかママの疲れが増える…。
「朝はなかなか起きてこない」「宿題は後回し」「気づけば一日中テレビやゲーム」——。
小学生の冬休みは、楽しい反面、親にとっては“時間との戦い”でもあります。
せっかくの休みを、子どももママも心地よく過ごすためには、「頑張らなくても続けられる1日の流れ」を作ることがポイント。
この記事では、在宅ワークや家事と両立しながらも、子どもが自然と動き出す“ゆるスケジュール”の作り方を紹介します。
冬休みに“ダラダラ”してしまうのはなぜ?
生活リズムの崩れが引き起こす悪循環
冬休み中は登校時間がなく、どうしても朝がゆっくりになりがち。
夜更かしが増えると朝起きられず、朝食が遅れて昼食も遅くなり——と、生活リズムがズレていきます。
このズレは、単なる「時間の問題」ではなく、集中力や気分の波にも影響します。
朝のうちに頭を使う習慣がなくなると、「やる気スイッチ」が入りづらくなり、結果としてダラダラとした1日が続くのです。
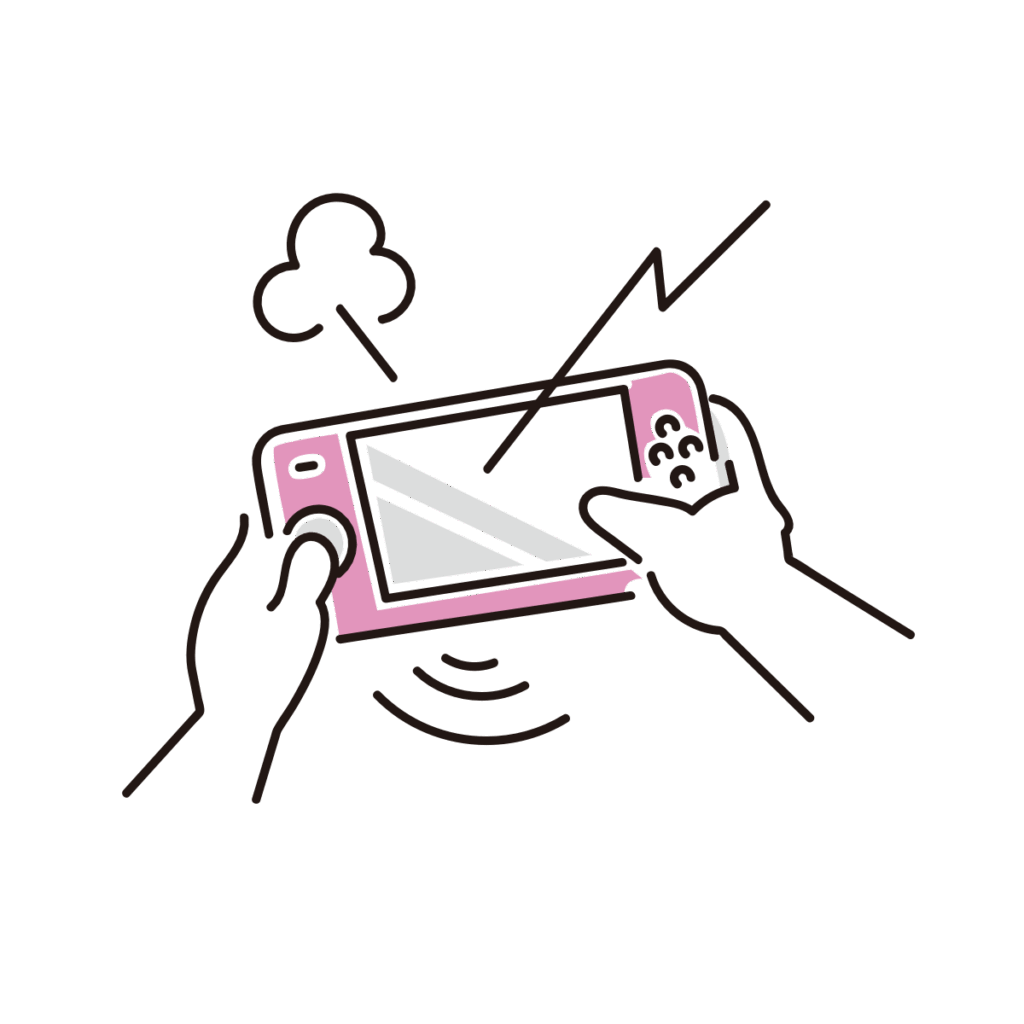
予定のなさが「やる気のなさ」に
小学生は、自分で1日の流れを組み立てるのがまだ苦手。
「今日は何をするの?」が曖昧なままだと、テレビやゲームに流れてしまいがちです。
ママが口うるさく言わなくても動けるようにするには、“見通しをもてる仕組み”が必要。
それが次に紹介する“ゆるスケジュール”です。
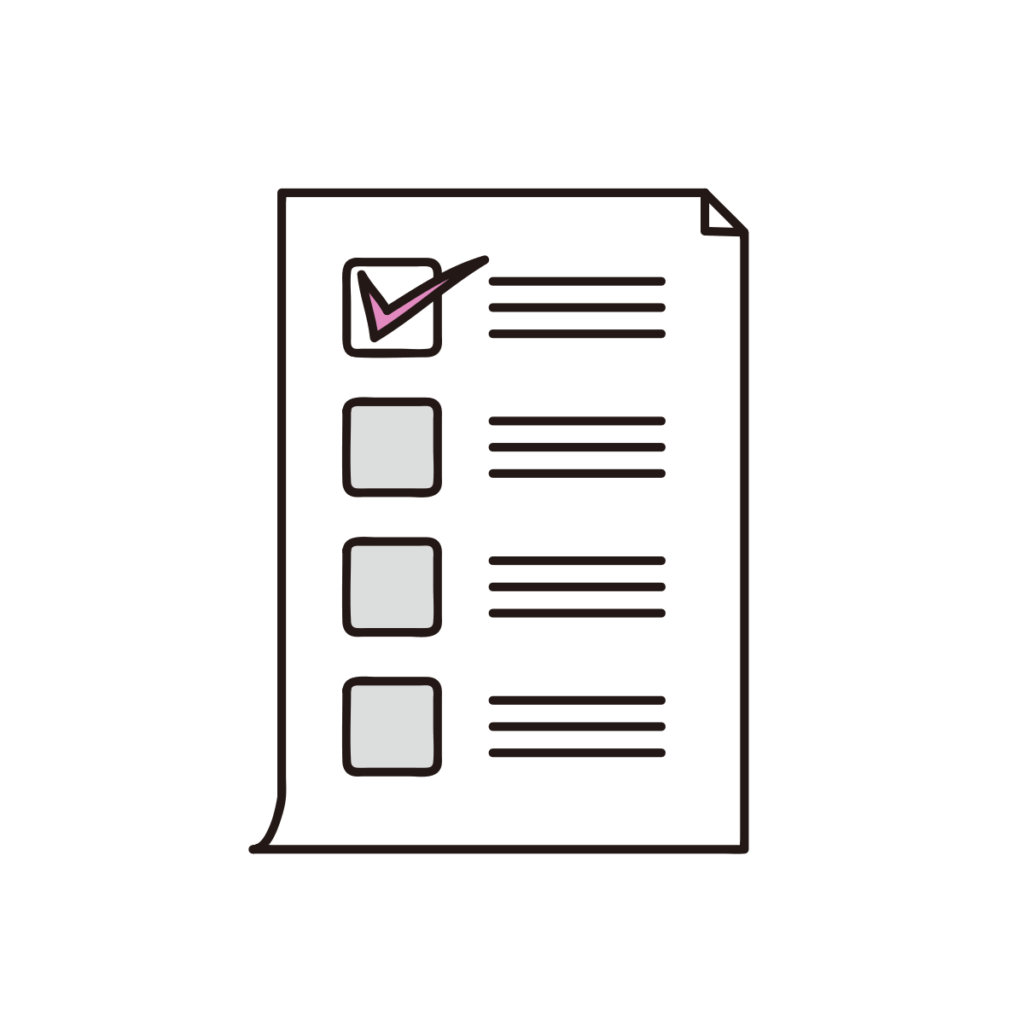
ママがラクになる“ゆるスケジュール”の作り方
ガチガチより“ざっくり時間割”が続く
冬休みの1日を、学校の時間割のようにきっちり決めると続きません。
ポイントは「大枠だけ決める」こと。
たとえば、こんな感じです。
時間帯 内容の目安
7:30〜8:30 起床・朝食
9:00〜11:00 宿題・お手伝いタイム
11:00〜12:00 自由時間(遊び・動画OK)
12:00〜13:00 昼食
13:00〜15:00 お出かけ or 工作・読書など
15:00〜17:00 ゲーム・テレビOKタイム
18:00〜 夕食・お風呂
20:30〜 就寝準備
これを「冷蔵庫に貼る」「ホワイトボードに書く」だけで、子どもが自分で時間を意識できるようになります。
家族みんなが1日に何度も目に付く場所に貼っておきましょう。
そうすることで、ママが「そろそろ宿題しなさい」と言う回数も自然と減ります。
“ごほうび時間”を上手に取り入れる
「宿題をやったら動画30分」「お手伝いしたらおやつタイム」など、短い区切りで達成感を味わえる仕組みを作るのもおすすめ。
特に冬休みは長期戦です。
「1日頑張ったら何かがもらえる」より、「午前中頑張ったら好きなことができる」くらいの軽いご褒美の方が、子どものやる気が続きやすいです。
ママの予定にも“余白”を
ママ自身も、スケジュールを詰め込みすぎないことが大切。
「昼食後は15分だけコーヒータイム」「子どもが工作している間は読書」など、自分の時間を小さくでも確保することが、穏やかな1日の鍵になります。
冬休みの早めの段階でルーティン化してしまうことで、時間が奪われることも少なくなります。
親子でストレスを減らす過ごし方アイデア
午前中に“やること”を済ませる習慣
午前中は、脳が冴えて集中しやすい時間帯。
宿題やお手伝いなど、“ちょっとめんどくさいこと”を午前中に片付けるのがおすすめです。
午後からは、お出かけや遊び、テレビなどの自由時間をたっぷりと。
「午前中頑張れば午後が楽しい」というリズムを作ると、子ども自身のモチベーションが自然と上がります。
子供自身も「今日はもう、お手伝いや宿題をやれた!」という自己肯定感アップにも繋がります。
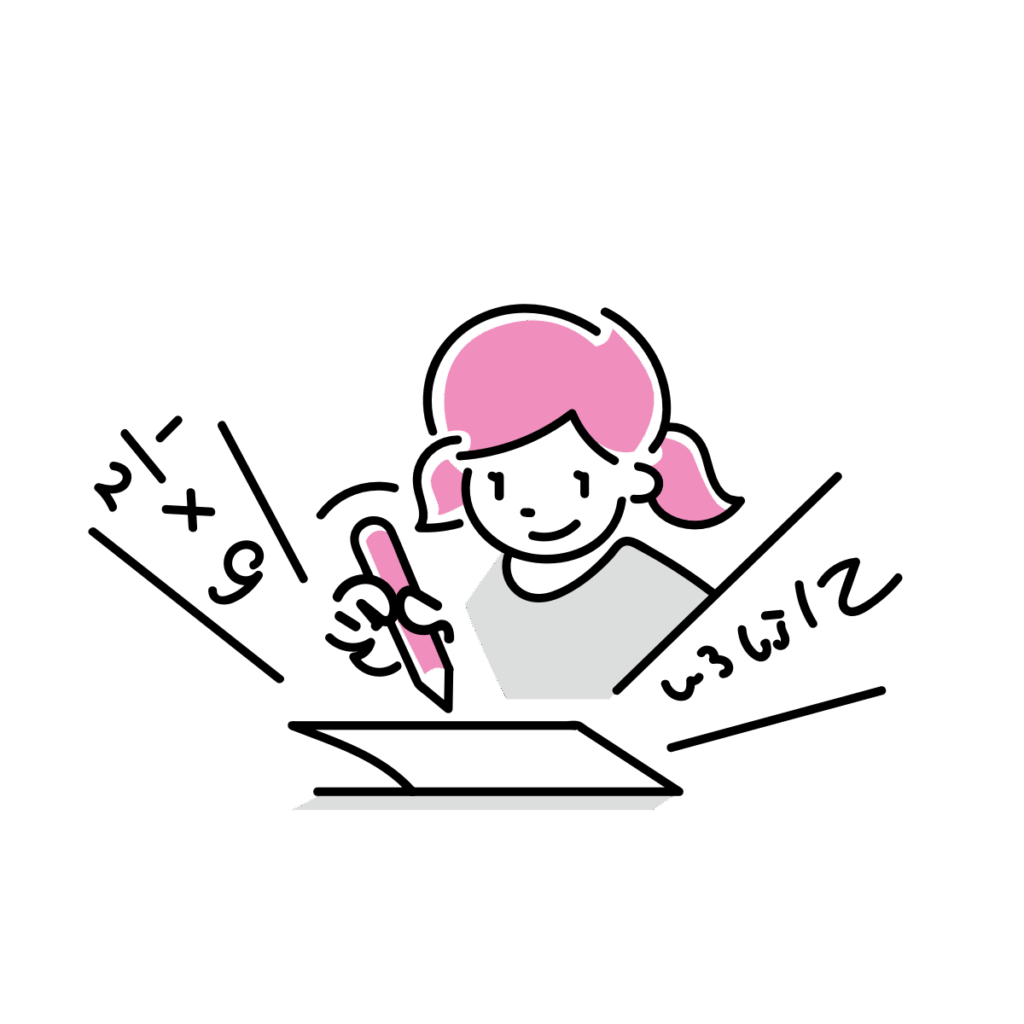
“一緒に過ごす時間”を短くても確保
冬休みは、ママも仕事の区切りをつけたり、年末の家事で忙しい時期。
ずっと一緒に遊ぶのは難しいですが、短くても“親子で笑顔になれる時間”を意識すると、子どもは満たされやすくなります。
たとえば
・おやつを一緒に食べながら今日の出来事を話す
・夕方、一緒にスーパーまで歩く
・寝る前に10分だけ本を読む
たったそれだけでも、「ママと過ごせた」という安心感が生まれ、無理なく良い距離感が保てます。
幼少期に親と接する時間が長かった子供は、前向きな思考になる傾向があります。
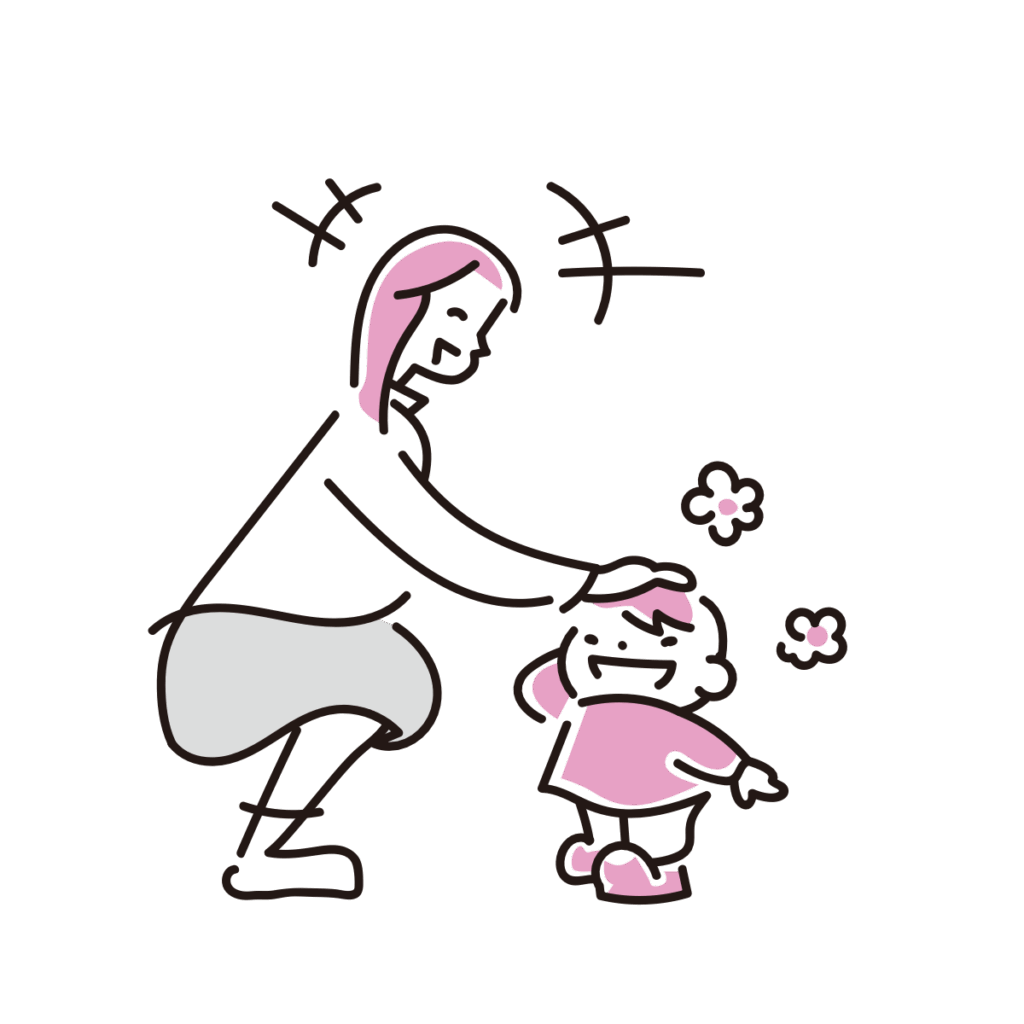
子どもを“手伝い戦力”に変える
お正月準備や大掃除も、子どもと一緒にやれば遊び感覚に。
「お正月飾りを並べよう」「玄関をピカピカにしよう」など、お手伝いを“イベント化”すると、家族の時間も増えます。
「ありがとう、助かったよ」と声をかけることで、子どもも達成感を感じ、「自分も家族の一員」として自信を持てるようになります。
冬休み明けをスムーズにするために
1週間前から「起床時間リセット」
冬休み終盤になってから焦らないために、1週間前から少しずつ生活リズムを戻すのがおすすめ。
最初は「朝10時起き→9時半→9時…」と、ゆるやかに調整していきましょう。
朝の時間に「日光を浴びる」「白湯を飲む」だけでも体が自然に目覚めます。
これはママの体調管理にも効果的です。
やりすぎない、完璧を目指さない
SNSを見ると、理想的な過ごし方をしている家庭が目に入ることもありますが、比べすぎないことが何より大切。
ママが「ちゃんとしなきゃ」と力を入れすぎると、子どももプレッシャーを感じます。
冬休みの目的は、勉強でも整理整頓でもなく、「家族がゆったり過ごすこと」。
“まあいっか”の気持ちを持てるママほど、家庭の雰囲気が穏やかになります。
まとめ|「がんばらない仕組み化」でママの心が軽くなる
冬休みは、親にとって試練のようで、実はチャンスでもあります。
家族全員のリズムを見直し、子どもが自分で考えて動ける力を育てる期間でもあるのです。
大切なのは、ママが一人で頑張ることではなく、「仕組み」でラクをすること。
• 朝の時間割をざっくり決めて見える化する
• “午前はやること、午後は自由時間”の流れを作る
• 短くても親子の時間を確保する
• 冬休み明けの1週間前から生活リズムを戻す
この4つを意識するだけで、家の中がぐっと穏やかになります。
▶行動の一歩
今日のうちに、冷蔵庫のホワイトボードに「明日のざっくり時間割」を書いてみましょう。
たったそれだけでも、冬休みの“ダラダラ防止”が始まります。
ママが少しラクになれば、家族みんなが笑顔で過ごせる冬になりますよ。
こちらの記事もおすすめ!


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e2accfb.01500bfc.4e2accfc.996227b5/?me_id=1408708&item_id=10000328&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flotteshop%2Fcabinet%2Fshouhin03%2Fkoalabox%2F12397175%2F251031_107059_thu.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e2ad21f.0941ac82.4e2ad220.80221a0f/?me_id=1227333&item_id=10015507&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Froomy%2Fcabinet%2F500cart_all%2F500cart_11g%2F7%2Fdss5000-rv021-0_gt01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b81901c.651ff146.4b81901d.f47ec06b/?me_id=1209653&item_id=10010337&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flow-ya%2Fcabinet%2Fitem_cart%2Foffice%2F01%2Ffz04-g1002-100_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


コメント